「ママ、あの人の周りがキラキラ光ってる!」「〇〇ちゃんはピンク色が見えるよ」…もしあなたのお子さんが、人の周りに色が見えるといった不思議なことを言い出したら、驚きと共に「これは何かのサイン?」「特別な能力なの?」と戸惑いや期待を感じるかもしれません。子どもの純粋な言葉だけに、どう受け止めたら良いか悩みますよね。
インターネットや体験談を見ても、「子どもの頃はオーラが見えていた」という話や、子どもの霊感、感受性の豊かさに関する話は少なくありません。一方で、それをどう捉え、親としてどう向き合っていくべきか、具体的な情報は見つけにくいかもしれません。この記事では、子どもがオーラを見ると言われる理由やその特徴、そして親として知っておきたい適切な向き合い方や注意点について、スピリチュアルな視点も交えながら解説していきます。
なぜ子どもはオーラが見えやすいと言われるの?考えられる理由

大人はなかなか見ることができないオーラを、なぜ子どもは見やすいと言われるのでしょうか?いくつかの可能性が考えられています。
理由1:純粋さと固定観念のなさ

子どもたちは、大人のように「オーラなんて見えるはずがない」「非科学的だ」といった固定観念や先入観を持っていません。そのため、目に見えないエネルギーや微細な光を、フィルターを通さずに純粋な感覚で捉えやすいと言われています。感じたままを素直に言葉にできるのも、子どもの特徴です。
理由2:高い感受性と直感力

多くの子どもは、大人よりも感受性が豊かで、五感以外の感覚(直感など)も鋭敏です。人の感情の微妙な変化や、場の雰囲気、エネルギーの流れなどを敏感に察知する能力が高いとされています。その鋭敏な感覚が、オーラのようなエネルギーフィールドを色や光として認識させているのかもしれません。
理由3:スピリチュアルな能力(霊感)の名残?

スピリチュアルな視点では、人は皆、生まれた時には霊的な世界との繋がりを持っていると考えられています。成長するにつれて、現実世界への適応や論理的思考の発達と共にその能力は薄れていくことが多いのですが、一部の子どもにはその感覚が強く残っているため、オーラや他の目に見えない存在を認識しやすい、という説もあります。
理由4:共感覚(シナスタジア)の可能性

「共感覚」とは、ある刺激に対して別の感覚が自動的に引き起こされる現象です(例:文字に色が見える)。これと同様に、「人」や「感情」に対して特定の色を感じる共感覚を持つ子どもがいます。その子どもにとっては、人が特定の色をまとって「見える」のが自然な知覚であり、それを「オーラが見える」と表現している可能性があります。共感覚は病気ではなく、脳の個性と考えられています。
オーラが見える子どもの特徴(一般的に言われること)

もしあなたのお子さんにオーラが見えているとしたら、どのような特徴が見られる可能性があるでしょうか? 一般的に言われる特徴をいくつかご紹介します。
特徴1:色彩への強い関心・独特の色使い

色に対して非常に敏感で、特定の色に強い好みやこだわりを見せることがあります。また、お絵描きなどで、人の周りに特定の色を描き加えたり、太陽や空など、通常とは違う色で表現したりすることがあります。これは、彼らが見ている世界の色を反映しているのかもしれません。
特徴2:人の感情や雰囲気に敏感

周りの大人の気分や感情の変化、その場の空気感を素早く察知します。機嫌の悪い人や悲しんでいる人に気づいたり、逆に楽しそうな人のそばに行きたがったりすることがあります。初めて会う人に対しても、好き嫌いや警戒心をはっきりと示すこともあります。
特徴3:想像力豊かで空想好き

目に見えない世界やエネルギーを感じやすいためか、想像力が非常に豊かで、ファンタジーや物語の世界に深く没入することを好みます。空想のお友達がいたり、一人で空想の世界に入り込んで遊んでいたりすることも多いかもしれません。
特徴4:独特の表現や発言

大人には理解しにくい、独特の言葉や表現で自分の感じていることを伝えようとすることがあります。「あの人、ピカピカしてる」「〇〇先生は青い感じがする」「ここ、なんかモヤモヤする」など、オーラやエネルギーの状態を描写しているかのような発言が見られるかもしれません。
特徴5:人混みや特定の場所を嫌がる

感受性が高いため、多くの人のエネルギーが混ざり合う人混みや、騒がしい場所、あるいはネガティブなエネルギーが溜まっていると感じる場所を本能的に嫌がり、行きたがらないことがあります。逆に、自然の中など、心地よいエネルギーの場所では安心し、生き生きとする傾向があります。
※注意点: これらの特徴はあくまで一般的に言われる傾向であり、これらに当てはまるからといって必ずオーラが見えているとは限りません。HSP(Highly Sensitive Person)など、他の気質や特性と共通する部分もあります。一つの可能性として捉えることが大切です。
子どもが「オーラが見える」と言った時の親の向き合い方・注意点

もしお子さんがオーラについて話し始めたら、親としてどのように向き合うのが良いのでしょうか。慌てず、子どもの気持ちに寄り添うためのポイントと注意点をまとめました。
1. 頭ごなしに否定しない

最も大切なのは、子どもの言葉を否定しないことです。「そんなの嘘だよ」「見間違いでしょ」「変なこと言わないの」といった反応は、子どもを傷つけ、自分の感覚を信じられなくさせてしまいます。まずは「そうなんだね」「へえ、どんな風に見えるの?」と興味を持って受け止め、話を聞いてあげる姿勢を示しましょう。
2. 過度に特別視・詮索しない

「うちの子は特別なんだ!」と過度に興奮したり、周りに吹聴したりするのは避けましょう。また、「誰のオーラが見える?」「あの人は何色?」「もっと詳しく教えて!」などと根掘り葉掘り聞くのも、子どもにプレッシャーを与えてしまう可能性があります。子どもにとっては、それが当たり前の感覚である場合もあります。あくまで自然な態度で接しましょう。
3. 不安や恐怖を取り除く

もし子どもが見えているもの(オーラに限らず)に対して恐怖や不安を感じているようであれば、まずはその気持ちに寄り添い、安心させてあげることが最優先です。「怖かったね」「でも大丈夫だよ」「ママ(パパ)がそばにいるからね」と、温かい言葉と態度で安心感を与えてあげてください。
4. 周囲への配慮を教える

オーラの話は、誰にでも理解されるわけではありません。状況によっては、他の人の前でオーラについて話すのは控えるように、TPOをわきまえることを優しく伝える必要もあるでしょう。これは、他者を不快にさせないため、そして子ども自身が周囲から奇異な目で見られたり、傷ついたりするのを防ぐためでもあります。
5. 子どもの感覚を守る環境

もしお子さんが人混みや特定の場所を極端に嫌がるなどの行動が見られる場合は、その感覚を尊重し、無理強いしないようにしましょう。なるべく安心できる穏やかな環境を整えたり、自然に触れる機会を増やしたりするなど、子どもの感受性に配慮した対応を心がけることが大切です。
6. 利用しようとする人からの保護

残念ながら、子どもの「特別な能力」を興味本位で利用しようとしたり、場合によっては金銭的な目的で近づいてきたりする大人もいるかもしれません。親として、そうした可能性も念頭に置き、子どもの純粋な感覚が悪用されないよう、しっかりと見守り、保護するという強い意識を持つことが重要です。
7. 医学的な可能性も視野に(必要な場合)

非常に稀なケースですが、「色が見える」という訴えが、目の病気(光視症など)や他の医学的な問題に関連している可能性も完全にゼロではありません。もし、視界に関する他の異常(目の痛み、かすみ、視力低下など)を伴う場合や、親としてどうしても気になる場合は、念のため眼科医などの専門家に相談することも選択肢の一つです。ただし、安易に病気と結びつけて、子どもを不安にさせないよう注意が必要です。
オーラ視の能力は成長とともに変化することも

子どもの頃にはオーラが見えていたけれど、大人になるにつれて見えなくなった、という話はよく聞かれます。これは、成長過程で論理的な思考や社会性が発達し、現実世界への適応が進む中で、感覚的な能力やスピリチュアルな繋がりが自然と薄れていくためと考えられています。多くの場合、これは異常なことではなく、ごく自然な発達のプロセスの一部です。
たとえオーラが見えなくなったとしても、子どもの頃に培われた豊かな感受性や直感力は、形を変えてその子の個性や才能として残ることも少なくありません。大切なのは、オーラが見える・見えないという能力の有無で子どもの価値を判断するのではなく、その子自身の個性や感性を大切に育んでいくことです。
まとめ

子どもが「オーラが見える」と言う時、それは彼らの純粋さ、豊かな感受性、直感力、あるいは共感覚といった様々な要因が背景にあるのかもしれません。親としては、その言葉を頭ごなしに否定せず、かといって過度に特別視することもなく、まずは子どもの感覚を温かく受け止め、見守る姿勢が大切です。
子どもの安心感を第一に考え、必要に応じて周囲への配慮を教え、外部からの不適切な関心から守ってあげることも親の重要な役割です。オーラ視の能力は成長と共に変化することもありますが、その有無に関わらず、子どもが持つユニークな感受性そのものを尊重し、健やかな心の成長をサポートしていくことが何よりも重要と言えるでしょう。
この記事が、オーラが見える(かもしれない)お子さんとの向き合い方に悩む親御さんにとって、少しでも参考になれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【参考記事】オーラの色や意味についてもっと知りたい方はこちら▼
| オーラカラーの解説 | |||
|---|---|---|---|
 |
|||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
グリーン |
 |
 |
 |
 ゴールド |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|||




 オーラがある人
オーラがある人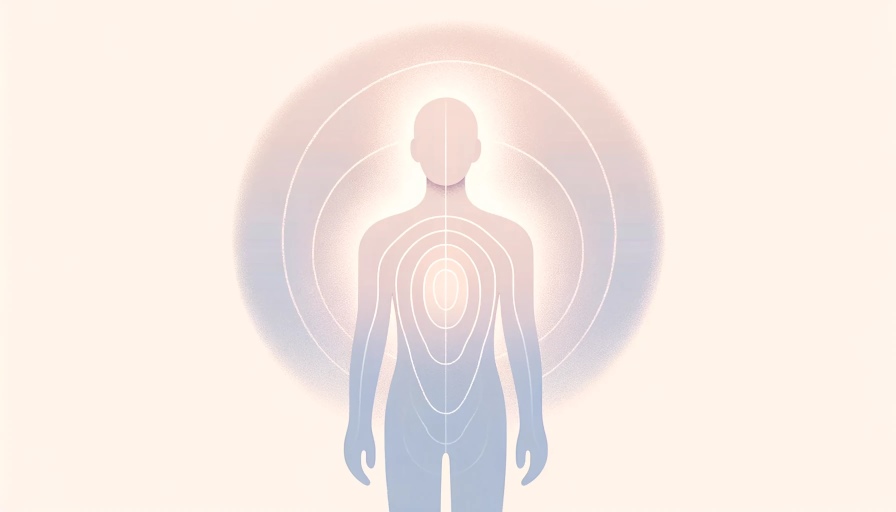

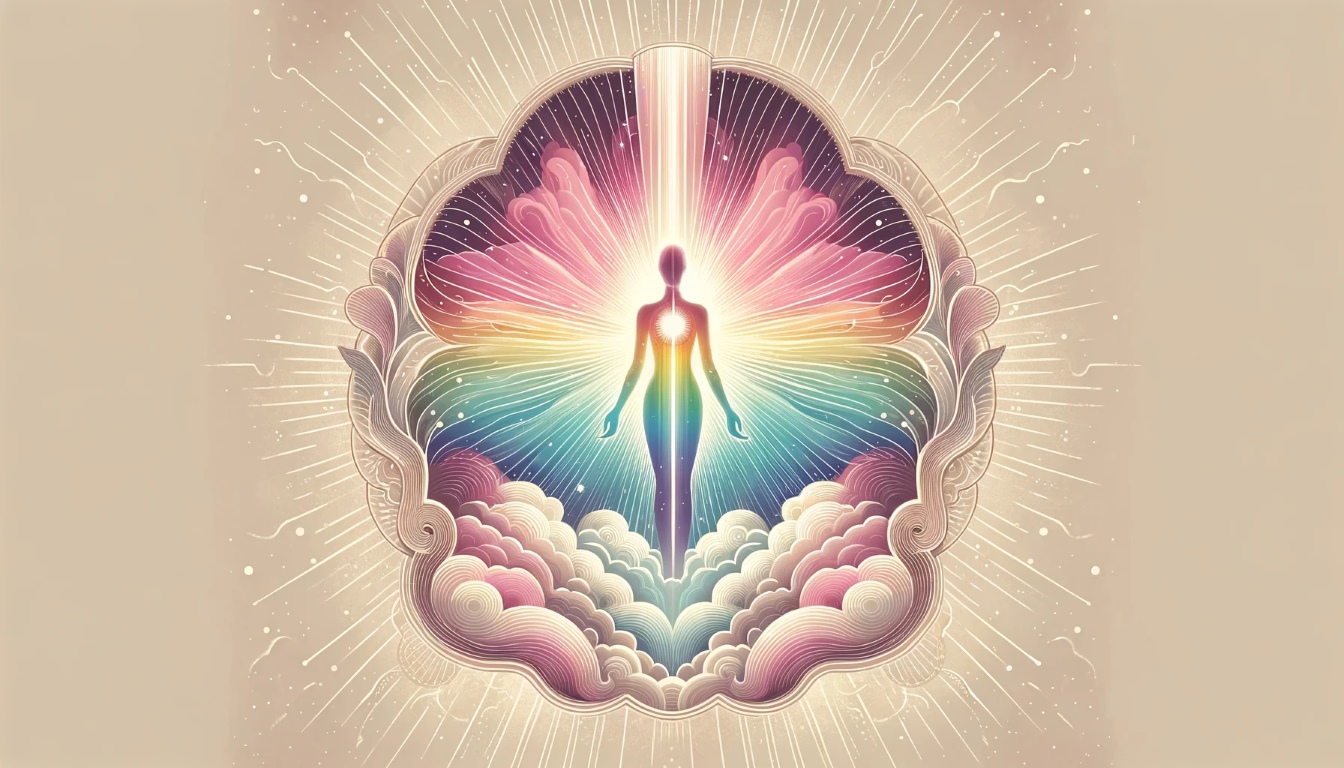





















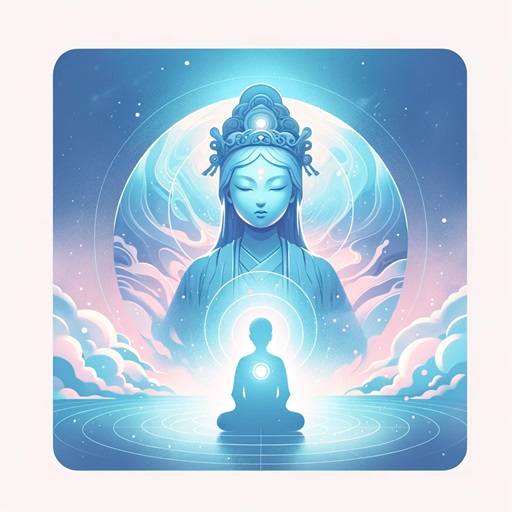
コメント